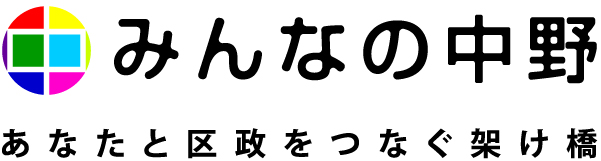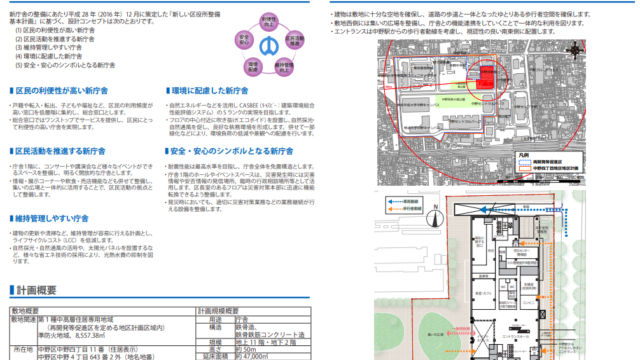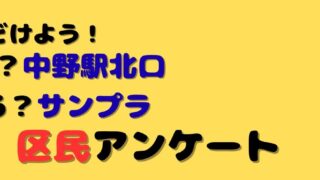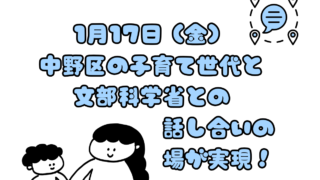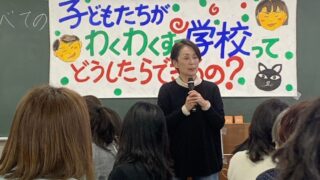中野駅北口再開発について、区民の声・中野から「酒井区長への要望書」を出すことになりました。
→追加:酒井区長に提出、話し合いの場をいただきました!
要望書の趣旨は以下3点です。
- 中野駅前再開発について、コンセプトや事業スキームを変えずに別の開発計画をつくるのではなく、「コンセプトや事業スキームから練り直す」ことを求めます。
- その際、「区が作る新たな計画を区民に丁寧に説明する」のではなく、「区民とともに考え、区民とともに決めていく」ことを求めます。
- 私たち区民の声・中野と、この要望事項について、じっくり話し合う場を設けることを求めます。
話し合いの日程を調整、続報をお待ちください。
中野区の皆さんの声を引き続きお願いします。
酒井区長への要望書
中野区長 酒井直人殿
中野駅北口再開発の進め方に関する要望書
2025年5月1日
区民の声を聴く中野区政を実現させる会 共同代表:松井奈穂、韮澤進
要望事項
私たち区民の声・中野は、中野駅北口再開発の進め方に関して以下の3点を要望します。
- 中野駅前再開発について、コンセプトや事業スキームを変えずに別の開発計画をつくるのではなく、「コンセプトや事業スキームから練り直す」ことを求めます。
- その際、「区が作る新たな計画を区民に丁寧に説明する」のではなく、「区民とともに考え、区民とともに決めていく」ことを求めます。
- 私たち区民の声・中野と、この要望事項について、じっくり話し合う場を設けることを求めます。
要望事項の説明
私たち「区民の声・中野」は中野駅北口再開発について、自主ゼミで2回取り上げて意見を聞きましたが、「賛成もしないが反対もしない」という立場で推移を見守っていました。
しかし、野村不動産を中心としたグループの再開発事業計画が白紙になるという驚きの事態を受け、いろいろ考えました。
今回の「白紙」の直接の原因は建築費の高騰ですが、これは野村不動産を中心とするグループの再開発事業計画の白紙化にとどまらない影響があると考えます。具体的には、「市街地再開発事業」という「高層化することで床を増やし、その床を売って事業費を捻出する」という「再開発の事業スキーム」そのものが時代に合わなくなってきているのだと思います。このスキームでいくには、より高層化しないと採算が合わないという理屈になるからです。
一方、タワーマンションの乱立についても社会的な危惧の声が増えてきています。
「タワマンは地震などの災害のときにエレベーターが止まると陸の孤島化するのではないか」
「年月が経って修繕しようとしたときに巨額の修繕費が賄えないのではないか」
「オフィス需要が低下しているのにタワマンのオフィスがこれ以上必要なのか」
「タワマンの住宅を購入するのは富裕層や外国の人が多く、節税対策・投資目的・転売目的が中心で、実際に居住する人は少ないのではないか、それでは賑わいの創出にならないのではないか」
「投資目的等のタワマンは言わば金融商品であり、公共性のある駅前に金融商品を作ることは行政のやるべきことではないのではないか」
こうした危惧は、仮に市街地再開発事業のスキームが「より高層の建築が可能」という形に緩和されたとしても、それで進めていいのかという問題をはらんでいます。
であれば、中野駅北口再開発は、単に野村不動産を中心とするグループの再開発計画が白紙になったから「別の再開発計画を提案してくれる事業者を探す」とか「高層建築を前提として採算が取れる計画を模索する」ということではなく、この際、高層建築にこだわらずに「再開発のコンセプトや事業スキームを含めて練り直す」べきなのではないかと考えます。これが要望事項の1番目です。
次に、中野駅北口再開発の再検討をしていくにあたっては「区が事業者とともに考えた新たな計画について、区民に丁寧に説明する」という進め方ではなく、「区民とともに考え、区民とともに決めていく」という進め方をとっていただきたいです。これが要望事項の2番目です。
区と事業者が作成した計画をどんなに丁寧に説明しても、それだけでは広範な納得が得られない状況であると考えます。その理由は、上述したタワマン乱立への危惧がマグマのようにたまってきているからです。どんなに丁寧に説明されても「感情的なモヤモヤが残ってしまう」という状況だと思います。
そこで、「中野駅北口再開発のコンセプトや事業スキームから練り直すことを、区民とともに考えて進める」という進め方を提案します。コンセプトから練り直すと宣言することで、「タワマンをつくる理由付けではないのね?」という受け止めになり、区民の側も、より冷静な受け止めができるようになると考えます。
また、「区民とともに考え、区民とともに決めていく」と宣言することで、「どういう再開発がいいのか?」という主体的な参画につながっていくと思います。
コンセプトや事業スキームを練り直してつくっていくという場合、たとえば以下のような複数の方向性がありうると考えます。
- 市街地再開発の事業スキームと「高層建築化の方向性を維持」したままで、新たな計画をつくる。サンプラザは都市計画に沿って解体する。
- 市街地再開発の事業スキームはやめて、「低層での再開発」にする。サンプラザは都市計画に沿って解体する。低層再開発は、たとえば文化芸術の発信拠点とする。
- 都市計画を見直し、サンプラザを残し区民のための施設と文化芸術の発信拠点と商業施設とホールで運営していく。
- 都市計画に沿ってサンプラザは解体するが、解体した後は建物をほぼ建てない。森と公園と広場と雨天時の区民の居場所だけにする。
他にも斬新な方向性があるかもしれません。いずれにしても、百年に一度の再開発事業なのですから、いろいろな可能性を排除せずに区民とともに考えていくことを提案します。
このような様々な方向性を区民とともに考え、区民とともに決めていくというプロセスを進めていく上では、それぞれの方向性について以下のような要件を区民にわかりやすく開示することが大切だと考えます。
- それぞれの方向性で、イニシャルコストとランニングコストの試算および区の財政への影響はどうか?
- それぞれの方向性で、手続きにかかる年数は? かかる年数に応じた区の財政への影響はどうか?
- それぞれの方向性で、中野駅の新改札口や南北通路や歩行者デッキなど、すでに工事が始まっている事業との関連性は? また、中野駅周辺で進められている再開発事業との関連は? 人気のある中野5丁目のにぎわいは中野駅北口やその周辺の再開発でどうなっていくのか?
- それぞれの方向性で、中野駅北口に人が集まるようになる度合い・にぎわいの創出度合いはどう違うか?
- それぞれの方向性で、環境への負荷の度合いはどう違うか?
- それぞれの方向性で、防災機能としての度合いはどう違うか?
- それぞれの方向性で、百年後に「負の遺産」となるリスクの度合いはどうか?
このような様々な方向性を区民とともに考え、区民とともに決めていくというプロセスを進めていく上では、以下のような取組みが必要だと思います。
- 中野区として中野駅北口再開発に関して、「コンセプトや事業スキーム」から「区民とともに考え、区民とともに決めていく」ことを宣言する。
- 専門家とともに区民も参加するパネルディスカッションとか、ワークショップなど「区民とともに考える場」を区の主催で開催していく。
- 前項の7つの要件についての評価を区民に開示し、評価の妥当性について区民の意見を聞く。
- 「区民とともに決める」ということを実現するためのプロセスをつくる。具体的な方法論は知恵を出し合いましょう。
こういう進め方には時間がかかりますが、今は急ぐ時ではないと考えます。むしろしっかり時間をかけることで、いい方向性ができていくと考えます。
酒井区長は、2018年の区長選挙の時、「対話の力を活かす区政へ」という理念を掲げ、
「区民の皆さんの声を聞き、【対話】を通じて、政策としてまとめてまいります」
「区長がやりたい開発から区民が必要とする開発への転換を進めます」
と公式ウエブサイトで述べられています。
この理念に基づきタウンミーティングや子育てカフェなど多くの対話の場を実践してこられています。今回の中野駅北口再開発こそ、この「対話の区政」という理念が最大限に活かされるべき時です。中野区民を信頼し、中野駅北口の再開発について「区民とともに考え、区民とともに決めていく」という決断を心から求めます。
まずは、私たち区民の声・中野と、この要望事項について、じっくり話し合う場を設けていただきたいです。
以上。
問合せ先:韮澤進 080-6861-8080 tongarapipaopao@gmail.com